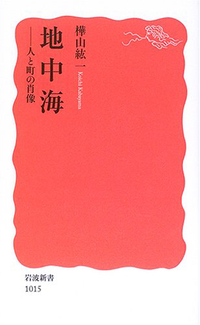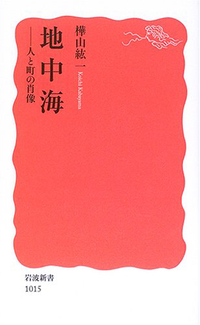
ブルクハルトの解説を書いているのが著者であるが、その中でブルクハルトは易しいと憎らしいことを言っている。こちらは何度読んでも歯が立たないというのに。
幸い本書は読みやすい。樺山の他の文章とは一味違う文体で一貫していて、優雅というか泰然としている。地中海周辺の歴史を人物像から描く。6っのテーマ各々に2人を配して。
歴史(ヘロドトス、イブン・ハルドゥーン)科学(アルキメデス、プトレマイオス)聖者(アントニウス、ヒエロニムス)真理(イブン・ルシュド、マイモニデス)予言(ヨアキム、ノストラダムス)景観(カナレット、ピラネージ)
こうしてみると、当たり前だが地中海の歴史は西欧側だけの視点では捉えられないという事がわかる。イスラム・アラブにも強くないといけないのだ。その意味で、この12人の中で、誰だっけ?と思わせるのが、真理の項のイブン・ルシュドだ。
コルドバでユダヤ人マイモニデスとともに活躍したイスラム学者。アリストテレス全集をアラビア語に訳した人だ。後のパリ大学のアリストテレス理解は、アラビア語経由でラテン語世界にもたらされたものだ。樺山は狡猾にも、最後のほうでそっとイブン・ルシュドは、またラテン語でアヴェロエスと呼ばれた、と書くのだ。
パリ大学はアヴェロエスが取り組んだ理性と信仰の分離を更に進めた。現代にまで続く「二重真理論」問題である。
私は若い時、2人の優れた理論物理学者と親交を得たことがある。ひとりは日本人、ひとりはドイツ人。2人とも超頭のいい人だったが、共通点は、敬虔なキリスト者だったことだ。ひとりはカトリック、ひとりはプロテスタントだが。いかにしてこの2人の頭脳は信仰と調和できるのか、それはいまだに私を捉える疑問である。

 日記/一般| 浜松市|
日記/一般| 浜松市|